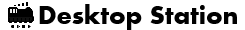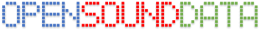OPEN SOUND DATA - 説明書・サポート
サポートについて
サポートは、一切提供されません。ESU LokSound向けサウンドデータは自己責任で使用してください。ESU社のサポートも受けることができません。
使用方法・マニュアル
LokSound向けのマニュアルの提供は終了しました。ご自身で付属の説明書をお読みいただき、対応ください。サポートはございません。
デコーダの入手・書き込み方法・サポートについて
LokSoundで使用される場合は、自身の力で調べてご利用ください。サポートはありません
オープンサウンドデータの管理・運営
オープンサウンドデータは、Desktop Stationと有志による運営となっております。